ストレッサー(ストレス源、負荷のこと。つまり、騒音、蒸し暑い天気、 嫌な音、臭いなど)に曝された時、我々の心身には様々な変化が 起きるとされています。 それが、 ストレス反応と呼ばれるものです。
ストレス反応について
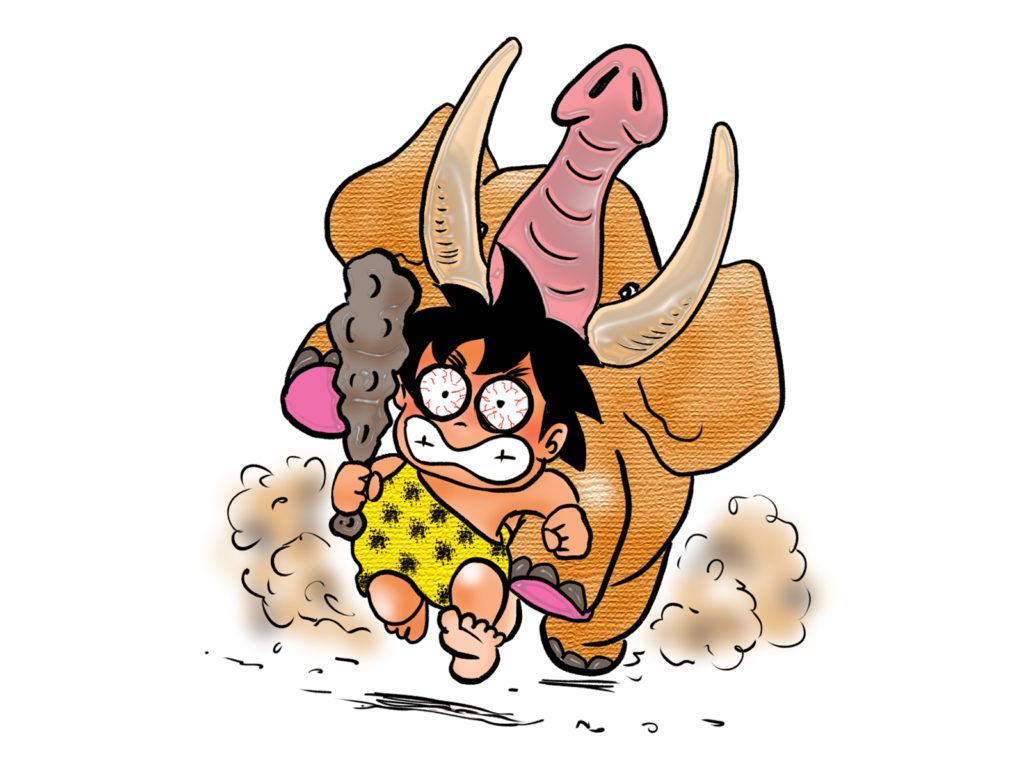
まず、マンモスと戦っている時の事を一度想像していただくと、そのときの心身の反応に想像がつきやすいかと思います。
もしマンモスと戦わなければいけない時代に生きていたら、ヘナヘナな状態ではたちまちに吹き飛ばされてしまう事でしょう。そのため、マンモスと戦う際には、心身をみなぎらせておくものです。目を見開き、手には力を込め、足も即座に動けるよう交戦体制です。しだいに汗が流れ、心拍数も上がっています。気持ちの上では興奮状態です。
戦闘態勢
医学上は、交感神経優位の状態です。戦闘態勢なのです。これも生きる中では必要な態勢なのです。(逃げるのも一つですから、逃走態勢とも言えます)
しかし、マンモスと戦った数時間後の晩には、すっかり疲れている事でしょう。もうマンモスは近くにいませんし、食事も終えて、ゆっくりと家族で焚火にでもあたって星空でも眺めているわけです。
こんなときは、うとうとしてしまいそうです。こういうときは、医学上は副交感神経の方が優位になっています。
これはリラックスしていると言えます。
マンモスの例がわかりにくいときは、スポーツの試合と置き換えて想像してみるのも良いでしょう。
ラグビーやアメフトの試合中には心身をみなぎらせていることでしょう。

生理学者らの整理したストレス反応
セリエ博士やキャノン博士のような生理学者は、現代からはるか以前に、どのような変化が生じるかとという点を研究していた歴史もあります。 さて、一般に、心理的な反応、行動的な反応、身体的な反応がストレッサーに よって生じてくるものであり、それは概ね下記のようになる。
心理的な反応

- 不安感や気分の落ち込み
- いらいら
- 怒り などが生じる。長期化すると無気力やうつ気分も出現。
イライラ日常場面と重ねて想像してみると、我々は、騒音をずっと聞いていると、 いらいらして外に向かって「うるさい!」などと大声を挙げるようなことがないだろうか。 これもストレス反応と言えるであろう。
行動的反応

- 集中力の低下
- 眠れない
- 喫煙の増加
- 性欲や意欲の減退 など
ストレッサーは、行動にも影響し、集中力の低下などを招くことになる。 試しに、単純な計算問題をストレッサーが「ある」、「なし」の条件別で 行ってみると、ストレッサーがある方では、ケアレスミスが増えるはずである。
身体的反応

- 心拍数の増加
- 体の緊張
- 発汗 など 長期化すると、頭痛、めまい、肩凝りなども出現
ストレスの身体反応はじめは、体に力が入る程度に感じていたものも、時間が長くなると、 頭痛までつながることがあるのではないだろうか。 ずっと嫌な臭いを我慢していたら次第に頭が痛くなりそうなものである。
別な体の不調との混同にも注意
以上が、ストレス反応の大まかな例のごく一部である。 我々の日常によくありがちなことが含まれている。 しかし、ストレス反応と別な身体的不調を勘違いしてしまうことは最も避けたいところであり、なんでもストレス 反応と決めつけるわけにはいかないものであろう。
ストレス反応の実感
ストレスマネジメント教育などにおいて、良く用いられる方法だが、ストレス反応に意識を向けるプログラムがある。例えば、リラクセーション実施前後で、脈拍を数えてみたり、単純な計算問題を行うなどである。 これにより、リラックス時と、緊張時での相違が視覚的に可能になる。ストレスはない、と感じていた人であっても、変化が生じることがあるので、普段の生活の中ではなかなか意識が向けられることは少ないようである。
ストレス反応をボールのへこみから理解する
さて、このストレス反応を説明する際ボールの例が用いられることがあります。
まず言葉を整理します。
- ストレス:元々、物理学用語。ここでは、「ストレス反応」と「ストレッサー」に分けられます。
- ストレス反応:ボールが変形した状態
- ストレッサー:ボールを押している原因なる存在
関連ページ:ストレッサーとその種類
平常時のボール

この青い玉を、人間(生体)と見立てます。
この状態が、最も充実してバランスの取れた状態と言えるでしょう。
この際、多少のストレッサーが加わっても、へこまないくらいかもしれません。
ストレッサーが加わったボール

ところが、赤い矢印のようなストレッサーがボールに負荷をかけると、ボールはへこんでしまいます。これがストレス反応なのです。
赤い矢印がなくなっても、しばらくボールはへこんだままです。
時間をかけて徐々に元の状態に戻ります。
日常生活でも緊張した後に、すぐにはドキドキが収まらないものです。しばらくして段々と平常に戻っていく経験をされていると思います。それがもとのボールに戻ったときのイメージです。
さらに慢性化すると専門的ケアが必要となるかもしれない
時間がたてば元に戻るのですが、このストレッサーが慢性化していたり、その強度が強いと、へこんだまま、なかなか元に戻らないことがあります。
赤い矢印も1本とは限りません。同時に複数の矢印が襲い掛かることもあるのです。
例えば、共働きで介護と子育てが同時に進行しているような状態では、日々相当な負荷を覚えるものです。そこにさらに、仕事のミスや残業、夫婦喧嘩などが上乗せされると考えたらやりきれません。
この辺りが、専門的ケアやなんらかの対処が必要な段階と捉える考え方があります。
まとめ
ストレス反応はストレッサーによって生じますが、そこは一定ではありません。ストレッサーの強度、コーピング、認知的評価、ソーシャルサポートなどによって、最終的に現れるストレス反応の程度が変化します。



