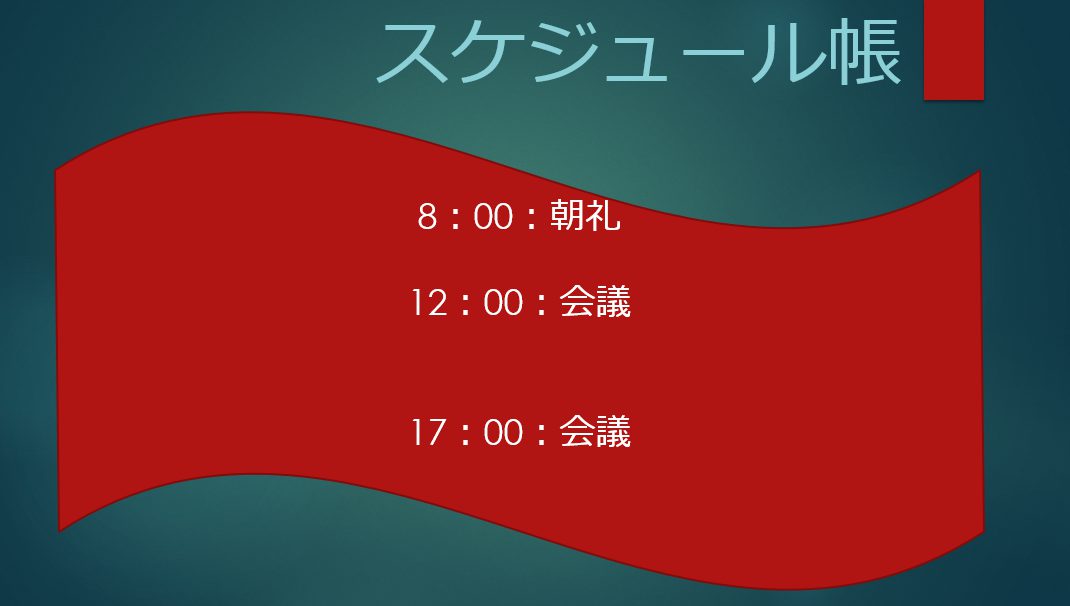最終更新日 2024年4月9日
シンクロニシティという言葉は、一つには、ユング心理学に触れる中で出会うことがあります。リフレーミングとはという記事を書きましたが、リフレーミングはテクニックやスキルという発想のもと用いるものではないだろうという所感を持っています。
考え方によると思いますが、リフレーミングが成立するには、シンクロニシティ体験のような、小手先でない何かがうごめいているように感じるからです。
カウンセリングの中で、別な見方として、物事に対するある見方をご提示することはありますが、その見方を押し付けることは最も避けたいことなのです。
シンクロニシティ体験
シンクロニシティとは、二つの出来事間にある意味のある一致のことを指す概念です。少し非科学的なのではないか?とお感じになる方もいるでしょう。
ある青年の体験
というような偶然が起きたときです。この青年は意識して木の下を選んだわけではなく、ましてその気がブナの木であることも知りませんでした。その木の下が最も落ち着いたということをこの青年がどう体験するかという点が注目されるところです。
このような体験のことをシンクロニシティと呼んでいいのではないかと思います。
カウンセラーはきっと伝えたくなる
冒頭の方で、リフレーミングをテクニックと考えていないというようなことを書いていますが、もし上記の青年がカウンセリングに訪れて、上記の語りを聞いていたとしたら、カウンセラー側にも、この青年はやはりピアノを続けたいのではないか?とか、この旅行はそれを確かめるために必要なことであったとか、ブナの木がそれを示してくれた、などという連想が自然と生じてくるわけです。
きっとカウンセラーは<そのエピソードは、ただの旅行の話というだけではないように聞こえます。私には・・・>などということを伝えたくなるでしょう。
こうしたときに、意味のあるやり取りがカウンセラーと青年の間で行われ、青年が旅行に出かけたということに、別な見方を提示できるのではないかと感じます。
なぜ!?今さらという数々の出来事
さて、また別な話ですがこのタイミングでなぜ!?ということが数々起こるものです。
またフィクション仕立てですが・・・ある青年の話です。
その青年の家では自宅で商売をやっており、取引先の人が頻繁に出入りしていました。
そして、色々な話をして帰って行くのです。それは仕事の話ばかりではありませんでした。
青年はその人たちが何の話をしているかなどまるで興味がなく、テレビを見ながらフンフンと言っていたばかりだったのです。
しだいに青年は年齢を重ね、チェスにはまったということでした。
しかし同年代にチェスの趣味を持つ人はなく、孤独と不全感を覚える日々を送っていたのです。
そんなとき、取引先の一人が実はチェス教室に通っていたことをいまさら知りました。
そして猛烈にチェスの話に興じました。
10年は付き合いのある人でしたが、このときはじめて知ったのです。
いや・・・話には出ていたのかもしれません。気にも留めていなかったということなのかもしれません。おそらくそっちが真実なのでしょう。

まとめ
このようなテーマは一つ一つ丁寧にお話を進める必要があるでしょう。ましてやカウンセリングにおいては尚更です。そうでなければ、きっと表面上のやり取りに終始する結果となるのではないかと感じます。